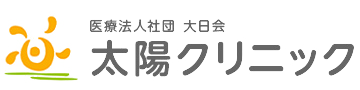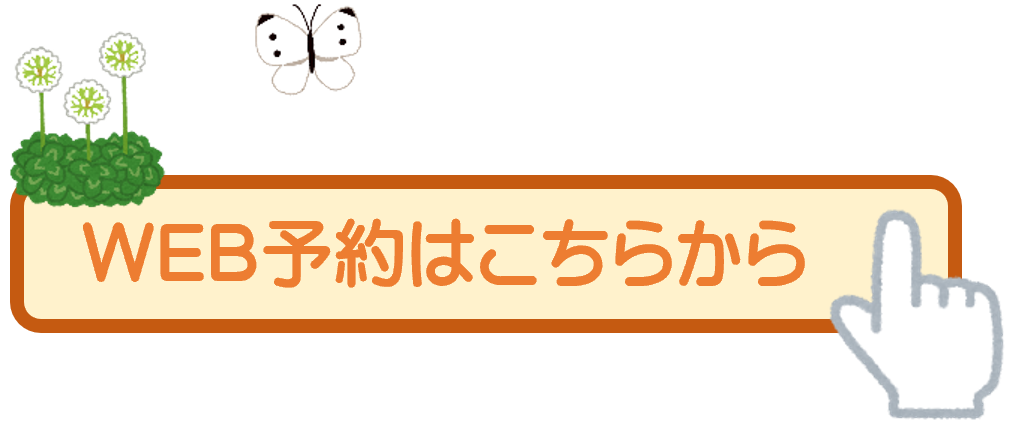マイコプラズマ感染症について
マイコプラズマ感染症は小児科診療ではしばしば見られる感染症です。かつては3-7年毎に流行を認めましたが、2000年以降その周期性は崩れています。2000年以降では、2011年-2012年に大流行があり、2015年-16年にも流行がありました。昨年2024年は1999年に現在の統計が始まって以来、過去最多の報告数となりました。2025年も患者数が多く9月の第4週の定点あたりの報告数が1.28人(都道府県によっては5.75人)となり、流行の波が続いている可能性があります。
感染しても、無症状で終わる場合が10-20%、急性上気道炎を発症する場合が50-70%、肺炎になってしまう場合が10-30%とされ、感染者が全て肺炎を起こすことはありません。予後は良好で重症化するのは珍しいとされています。発症年齢は5-15歳で最も多く、大学生・社会人にも発症します。5歳以下では感染率が低くなり、6ヶ月以下では少ないとされます。比較的年齢の高い子供に発症しやすい、胸部X線所見と比べて元気が良い、周囲の流行などから比較的診断しやすい感染症です。16-40歳では感染しても軽症で終わるとされています。高齢者でもまれに発症することがありますが、発症当初は微熱・食欲不振・倦怠感など、肺炎に気づきづらい症状が多いとされます。高齢者、基礎疾患がある場合には重症化する場合があり注意が必要です。 またマイコプラズマ感染は完全な免疫が獲得されないため、数年後に再感染することもしばしば経験します。最近の問題点は第1選択薬の抗菌薬である、クラリスロマイシンに代表されるマクロライドへの耐性化です。潜伏期間は1-4週です。
マイコプラズマ肺炎の症状---------
年齢による症状の違いはありません。病初期には発熱、倦怠感及び頭痛があり、咳は発症3-5日頃から出現し始め、当初は「乾いた、頑固な咳」と表現されます。その後は痰が絡む咳となって喘鳴を伴ってくることが多くなります。熱は39度前後になることが多く、5%前後で40度台になると言われます。頭痛は10%前後という報告もあれば、感染者の2/3とする報告もあります。鼻汁は少なく、もし認められればマイコプラズマ以外を疑うべきとする報告もあります。その他に嗄声、咽頭痛、胃腸症状、胸痛、結膜炎、などもあります。
肺炎以外の症状-----------
マイコプラズマ感染は肺炎以外にも多彩な症状を起こす場合があります。咳などの呼吸器症状を伴う場合もあれば、伴わない場合もあります。皮膚、中枢神経系の合併症が多いとされます。
①皮膚・粘膜系疾患
Stevens-Johnson症候群:皮膚の重症な発赤や紅斑、口唇・口腔・眼・外陰部などの粘膜の潰瘍を起こす重篤な皮膚反応です。皮膚・粘膜・眼症候群とも呼ばれます。Stevens-Johnson症候群は薬剤による症例(抗菌薬・抗てんかん薬・NSAIDSなど)が問題になりますが、小児ではマイコプラズマ感染が原因として一番多いとされます。呼吸器症状の出現から10日前後で、主に粘膜症状が出現します。皮膚症状は軽度なことが多いとされます。予後は薬剤性と比べて良いとされますが、眼の合併症で視力障害などの後遺症が残る可能性があり注意が必要です。マイコプラズマ感染では体の免疫反応が過剰になってしまい、自らの皮膚や粘膜を攻撃してしまうことがあります。その結果皮膚のただれや発赤、粘膜の潰瘍、39−40度の高熱などが出現します。
②難聴
感染症による難聴の原因としては流行性耳下腺炎が有名ですが、マイコプラズマ感染が2番目に多いと言われます。発症3日頃から2週間後に起きやすいと言われます。マイコプラズマ肺炎に伴う17例の難聴のうち8例が両側性の難聴で、9例に中耳炎や髄膜炎の合併があったという報告があります。急激に発症し突発性難聴と類似した経過を辿る、耳鳴りや目眩などの症状を併発することもあります。20-30%で聴力が完全に回復しなかった報告があります。ですから早期治療が大切で治療の遅れ、発症から1週間以上治療がされなかった場合、永続的な聴力障害が残る可能性があります。
③心血管系合併症
急性心筋炎:小児の急性心筋炎の原因は、夏風邪(手足口病、ヘルパンギーナ)などの原因となるエンテロウィルスが多いですが、マイコプラズマでも起こるとされます。マイコプラズマ感染における心合併症は1-数%との報告があります。他にも心外膜炎や不整脈の報告もあります。稀ではありますが小児や免疫機能が低下した人、高齢者では肺炎を伴わない急性心筋炎の報告がありますから注意が必要です。初期症状は発熱・倦怠感・上気道炎症状・消化器症状など非特異的な症状が主症状である場合も多く、診断が難しくなります。進行してくると呼吸困難、動悸、息切れ、胸痛、浮腫などの症状になってきます。
④血栓塞栓症
肺血栓塞栓症:マイコプラズマ感染により凝固亢進状態をきたし、肺血栓塞栓症を誘発したという報告があります。また脳梗塞、深部静脈血栓症なども報告されています。肺炎に続いて胸痛、呼吸困難、神経症状などの出現に注意してください。若年者の原因不明の血栓症ではマイコプラズマ感染に注意してください。発見が遅れると致命的になることもあるため、注意深い観察が必要になります。
⑤中枢神経系合併症
急性脳症・髄膜炎:急性脳症の全国調査では(2007年から3年間の983例)、マイコプラズマ感染に伴う症例が9例(1%)確認されました。他の報告では脳症に占めるマイコプラズマ感染の割合が6.5%でした。呼吸器症状出現後3−7日で痙攣・意識障害などが出現します。しかし一部の症例では咳を伴わない脳症も報告されています。脳症・髄膜炎では必ずマイコプラズマの可能性も考慮する必要があります。私もマイコプラズマ感染に合併した髄膜炎の経験がありますが、呼吸器症状は認めませんでした。
ギラン・バレー症候群:ギラン・バレー症候群はウィルスや細菌に感染後、自己免疫反応が起きて末梢神経が障害される疾患です。感染後1−3週前後で発症します。原因としてカンピロバクターが20-40%と最も多く、マイコプラズマは1-5%で決して多くありません。四肢の筋力低下を認めることが多いです。稀に呼吸筋麻痺を来し死亡する場合もありますが、カンピロバクターと比較し明らかに予後は良好です。γグロブリン大量療法などの適切な治療をすれば、数週から数ヶ月で完全に治癒することが多いです。予後を悪化させるものとして、呼吸筋麻痺がある、急速に進行する、高齢などがあります。
⑥消化器系疾患
急性膵炎:画像所見を欠く軽症例が多いと言われます。報告によると小児の急性膵炎の3.9%がマイコプラズマ感染によるとされています。一般的なウィルス性膵炎と同様に自然軽快する場合が多いようです。腹痛・嘔吐が主症状で、マイコプラズマ肺炎の発症後1ヶ月経過して膵炎を起こした症例が報告されています。
⑦運動器系疾患
横紋筋融解症:非常に稀な合併症です。マイコプラズマ感染以外にも、インフルエンザウィルス、レジオネラ、クラミジアなども原因となります。発熱、筋肉痛、筋力低下、倦怠感が主症状です。マイコプラズマ感染により骨格筋が破壊され、筋肉細胞内のミオグロビンが血液中に流出した状態です。結果として腎臓の尿細管壊死を起こし腎機能が低下します。ミオグロビン尿と言って赤褐色の尿になるのが特徴です。脱水があると発症しやいので、水分摂取を心がけてください。採血でASTやALT上昇、CK値が非常に高くなります。感染による免疫反応の活性化、IL6などの炎症性サイトカインの上昇が原因と言われています。
⑧血液疾患
血小板減少性紫斑病:マイコプラズマ肺炎の経過中または回復期に(発症7−14日前後)に皮下出血や紫斑、鼻出血が出現します。多くはマイコプラズマやITPの治療(ステロイドやγグロブリン大量療法など)で回復します。日本の報告では慢性化することは稀で、感染の治癒に伴い自然軽快することがほとんどとされています。
b血球貪食症候群:過剰な免疫応答を介して血球貪食症候群をきたすことがあります。マイコプラズマ肺炎後も高熱が改善せず、1週間前後で汎血球減少(白血球・ヘモグロビン・血小板全てが減少する)、肝脾腫、高フェリチン血症などが出現します。多臓器障害を伴うことがなければ、予後は悪くないとされます。抗菌薬やステロイド治療が必要になり、早期診断が重要です。
⑨急性腎不全
ネフローゼ症候群:多くは発症1−2週間後に検尿で血尿・蛋白尿を認め、一部の症例で浮腫・高血圧を伴ってネフローゼ症候群や急性腎不全を起こします。頻度は全体の数%前後ですが、臨床上重要な合併症です。多くは呼吸器症状の改善とともに自然回復しますが、中等症以上ではステロイド、場合によっては透析が必要になります。「発症から2週間以上経過して腎機能障害を合併する」という報告もあるため一ヶ月前後は注意します。
⑩中耳炎
診断---------
マイコプラズマ抗原迅速キット:鼻咽頭拭液からマイコプラズマ抗原を検出する方法です。15分前後で結果が判明しますが、感度が60-90%前後、特異度は90%以上とされます。感度とは、感染している人で陽性に出る割合、特異度は感染していない人で陰性と正しく出る割合です。感度があまり高くないですから、陰性でもマイコプラズマ感染を完全に否定できるわけではありません。
マイコプラズマLAMP法:PCR法と同様にマイコプラズマのDNAを直接検出する方法で 日本感染症学会によると感度92.9%、特異度が96.2%で信頼できる検査です。当クリニックでもこの検査を行なっています。
検体採取時の注意:検体採取時の注意点として、①深呼吸をしてから咳をしてもらい、出来るだけ気道の奥や気管由来の分泌物を採取する②咳・喀痰がよく出る時間帯に採取③咽頭後壁、鼻咽頭の奥の部分から採取するなどです。④当然、抗菌薬開始前に採取が必要で、発症1週間以内で採取をします⑤発症して早過ぎる時期は菌量が少なく偽陰性になってしまいます。
マクロライド耐性株の問題---------
日本では2000年以降、マイコプラズマ感染症治療の第一選択薬である抗菌薬のマクロライド耐性株の出現が問題になっています。日本の児童を対象とした全国調査で2012年に81.6%と報告され大きな問題となりました。以降抗菌薬の使用が控えられ、2019年の北海道での報告では16.3%にまで低下しています。しかしアジア全体で見ると今だ60%台と非常に高いレベルです。一方欧米では数%から10%程度とされます。
治療:耐性株の問題がありますが、日本小児科学会の提言では、クラリスに代表されるマクロライドが第一選択薬となります。何故ならばマクロライドの抗菌効果が大変強く、治療終了時には気道からマイコプラズが完全に除去されるからです。マクロライドで治療開始後2−3日以内に解熱しない場合には、耐性株を考慮してトスフロキサシンやミノサイクリンを考慮します。ミノサイクリンは骨発育不全や歯牙着色、エナメル質形成不全などの問題があるので8歳未満には使用できません。抗菌薬の投与期間はクラリス(マクロライド)で10日間、ミノサイクリンで7−14日、トスフロキサシンで7-14日が推奨されています。
参考文献
小児科vol.56.2015 769-773 田中ら
小児科vol.56.2015 809-816 丸金ら
小児感染免疫2013;25:247-254
Otology Jpn 2011;21:816-820
Acta Med Scand1979;206:77-86
Ann Intrn Med 1977;86:544-588
日本皮膚科学会雑誌2005;115:135-143
日本呼吸器学会雑誌2005;43:731-735
医療1993;47:205-210
小児科臨床2003;56:2051-2056
日本臨床2012;18:643-646
Emerg Infect Dis2012;18:849-851
Emerg Infect Dis.2017Oct;23(10):1703-1706
小児のマイコプラズマ肺炎の診断と治療に対する考え方
日本小児科学会 予防接種 感染症対策委員会
Textbook of Pediatric Infectious
Disease 8th edition 1976-2003
Auris
Nasus Larynx, 2019 Sano M et al.
臨血, 27: 8, 1986